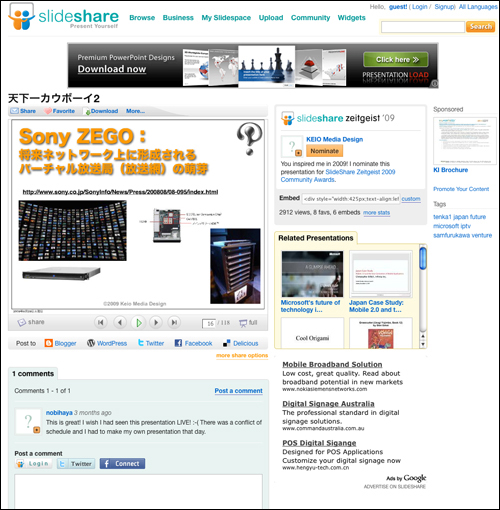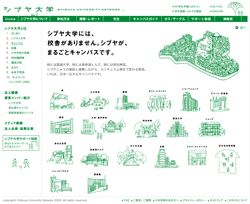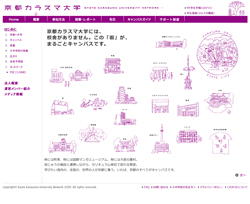第5回 HCD-Netサロン「インタラクションとHCD」が京都工芸繊維大学で開催されます。会員以外の学生も先着順で参加できるようです。卒業制作展開催中ですし、時間的にも京都市美術館の帰りに寄ると丁度いい感じ。インタフェースデザインに興味のある学生は是非申し込んでみてください。
日時:2010年 1月22日(金)16:30〜20:20(予定)受付16:15
会場:京都工芸繊維大学 東1号館5階E1-501
参加費: 会員:2,000円 一般:5,000円 学生:2,000円
定員:40名
詳細は下記サイトで。
http://www.hcdnet.org/event/hcd-net-salon/5_hcd-nethcd.php
2009.12.30[水]11:35 PM | UI Design
はちけんやガーデン前のあひるちゃん。
オランダのアーチスト:F.ホフマンの作品。
「かわいい」以外になんのメッセージも持たない、
単純に「かわいい」だけの圧倒的な威力。

そして、それをシンプルに伝える手法。

2009.12.16[水]1:13 AM | Memo
第1回ウェブ学会シンポジウムがさっきまでUSTREAMで中継されていました。
(アーカイブページ:午前・午後1・午後2・午後3)
私は友人からのメールで知ったんですけど、twitterで見つけて途中から参加した人も多かったみたいです。
質疑はtwitterでのみ受け付けるというのも含めて、会場に行かなかった人にとってもかなり臨場感のある会議でした。ライブに参加できるのって面白い。
8月に確か天下一カウボーイ大会のUSTREAM中継をたまたま見て、すごい!!って興奮して学生に話をしていたら、京都産業大学では大教室での講義にtwitter参加を取り入れたら出席率がとても良くなったという話を教えてくれました。大教室の講義系の授業って、ライブなのに参加感がなかったんだろうな。ウェブ学会のつぶやきもtwitterでは「#webgakkai」で辿れるけど、この種類のつぶやきはライブでないと散漫すぎて多分つまんない。なんなんだろうなぁ、この微妙な違い。。。
USTREAMのメニューには、Mobile、Sports、Entertainment、Gaming、Music、Animalsといっぱいあります。確かに、この辺がライブコンテンツと馴染みがよさそうだけど、一般企業の会議にもtwitter的なもの・USTREAM的なものを取り入れていくツール、必要だと思う。声の小さい人も参加しながら進行できる仕組み。動画だけじゃなくてスライドをシェアしながらという会議だってあるし。
午前中は会議で出かけていてシンポジウム見れなかったから、これからUSTREAM見ようと思ってます。


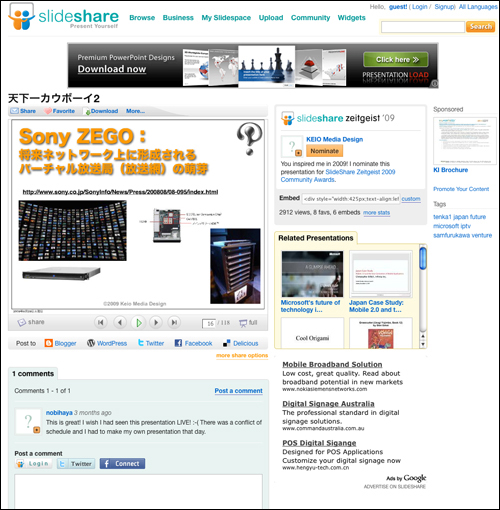
2009.12.07[月]8:31 PM | Memo,UI Design
[シブヤ大学]:学校教育法上の大学ではないけど、街歩きワークショップとかアート系ワークショップ中心のコミュニティキャンパス。こんなんあるんですね、知らなかった。「あ、京都にもあるじゃん、[京都カラスマ大学]」なぁんて思ったら、既に着々と全国展開中。
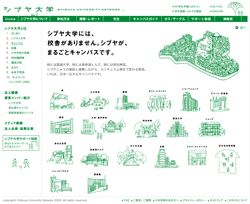
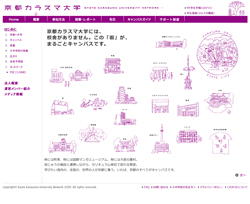
しかも、「シブヤ大学のつくり方学科 〜授業づくり編〜」なんていう授業もやっている。
なるほど〜。これも、フォーマット・ビジネスという考え方ですね。
昨日、秋元康さんがakb48をコンテンツ・フォーマットとして海外へ向けて販売しようとしている番組をやっていて、それにも「ほぉぉ」と思った んですが、仕組みとか仕掛とかをフォーマットとしてデザインして社会的価値を持たせて拡げていくやり方、こういうのってありですね。
秋元康さんのアイドル・コンテンツ・フォーマットは、Cool Japanともてはやされながら、アニメなどの大躍進していると思われているコンテンツ産業が実は全然日本に利益が入ってくるビジネスになっていない事に 対する「残念!」がベースになっていて、現場からの提案として説得力がありました。
「とりあえず保管箱・育成箱を作ればいいじゃん」…なんて思ってるコンテンツ業界や行政に対して痛烈なパンチ浴びせる行動力、すごいです。
で、たまたま見つけたのがシブヤ大学。コンテンツ・フォーマットという考え方、何もアイドルやアニメ業界だけに有効なアイデアじゃなくて、いろいろあるんですね。ちゃんと利益も生み出しながら、コミュニティを育てていくためのノウハウの共有という発想。いいな。
多分、こういうのも「メディア・デザイン」。
2009.12.06[日]5:37 PM | Memo
プロトタイプ展
東京ミッドタウン・デザインハブ
展示の手法がプロトタイプ展らしく、展示台になっているシナベニアにどの段階でのプロトであるとか、こういう意図で作成したとか、この辺の色の具合を再調整とかっていう解説が手書きで書かれていました。それぞれの出展者が展覧会コーディネータの指定を割と自由に解釈して記述されており、手書き文字の癖とともに人柄がでているというか、見ていて楽しかったです。
私は家電製品のインタフェース系のプロトタイプを期待していたのですが、そういう展示はほとんどなくて、家具中心だったのは少し残念。
丁度隣にあった九大のサテライトスペースでサイン学会が行われており、友人にばったりと出会っちゃったのにはびっくり。多分15年ぶりくらい。
医学と芸術展
森美術館
なかなか手が動かない仕事の参考にならないかと思って行った「医学と芸術展」。
「第1部:身体の発見」「第2部:病と死との戦い」については面白い資料や作品がいろいろあったのだけど、「第3部:永遠の生と愛に向かって」が若干期待はずれ。
「バイオテクノロジーやサイバネティクスや脳科学などに基づき・・・・生命とは何であるのかを医学資料やアート作品を通して考察します。」と書かれているのに、死や老化や障碍をテーマにした作品が並んでいるだけで、医学資料的な展示が少なく、バイオ医学はどこまで行ってもいいのかという倫理的な側面くらいしか印象に残らない。だからといってそこに焦点が絞られているわけでもなくて、なんだか散漫な感じ。
ダ・ヴィンチに始まる解剖学的な筋肉や骨格のメカニズムに関する表現の歴史は重要だし、生老病死や医学・科学をエロティシズム的観点から眺めた捉え方もあっていいとはもちろん思うんですが、展示の仕方のぶれなのか、第3部まで見終わっても「生命と愛の未来を探る」という副題に収斂されていっていないような印象をうけました。身体情報のセンシング技術や可視化の技術についてもっと見たかったんだけど…。
松丸本舗
丸の内オアゾ4F
空間の作り方がちょっと息苦しいくらいに迫ってきます。先に行った友人に聞いていたとおり、まさに松岡正剛さんの書斎に入っちゃったっていう感じ。展示の仕方は流石に面白くて、何時間いても飽きそうにない。
ただ、人の書棚から本を勝手に抜き出すような気がして、申し訳なくて買いたい気持になりにくいというのも友人が言っていた通り。
2009.12.03[木]8:50 AM | Memo